転勤が決まったときの持ち家の活用方法3選

転勤が決まった場合の活用方法として、以下の3つが挙げられます。
- 賃貸に出す
- 売却する
- 空き家にしておく
それぞれの特徴を理解し、自分や家族にとって最も良い方法を選びましょう。
賃貸に出す
まずは、転勤中に持ち家を賃貸に出す方法です。持ち家を賃貸に出す最も大きなメリットは家賃収入が得られる点で、数年後に持ち家に戻る予定がある方や、家が借り手の付きやすい立地にある方におすすめです。
ただし、賃貸中に修繕費や管理の手間が発生することや、空室が続くと赤字になってしまうことを理解しておく必要があります。持ち家を賃貸に出すかどうかは、賃貸需要や管理の手間を十分に考慮した上で判断しましょう。
売却する
持ち家の活用方法として、売却して現金化する選択肢もあります。持ち家を売却すれば住宅ローンや固定資産税などの負担がなくなり、住宅ローンの残債が少ない場合はまとまった資金が手に入ります。転勤期間が明らかでない方や、賃貸需要が低いエリアに家がある方におすすめの方法です。
一方で、売却に時間がかかったり、住宅ローンの残債が多い場合は不足分を自己資金から補填したりするケースがあります。売却を検討する際は、あらかじめ「いくらで売れそうなのか」「住宅ローンの残債はいくらなのか」などを確認しておきましょう。
空き家にしておく
転勤期間が1年以内など短期間の場合は、持ち家を空き家として残す方法もあります。空き家にしておく場合は特別な準備は必要ありませんが、固定資産税などの維持費はかかり続けることを理解しておきましょう。
また、防犯対策や定期的な管理も必要です。家に戻る時期が確定しているのであれば有効な方法ですが、いつ戻ってくるかわからない場合は、管理の手間や維持費が長期間続くことも考えられるため、慎重に判断する必要があります。
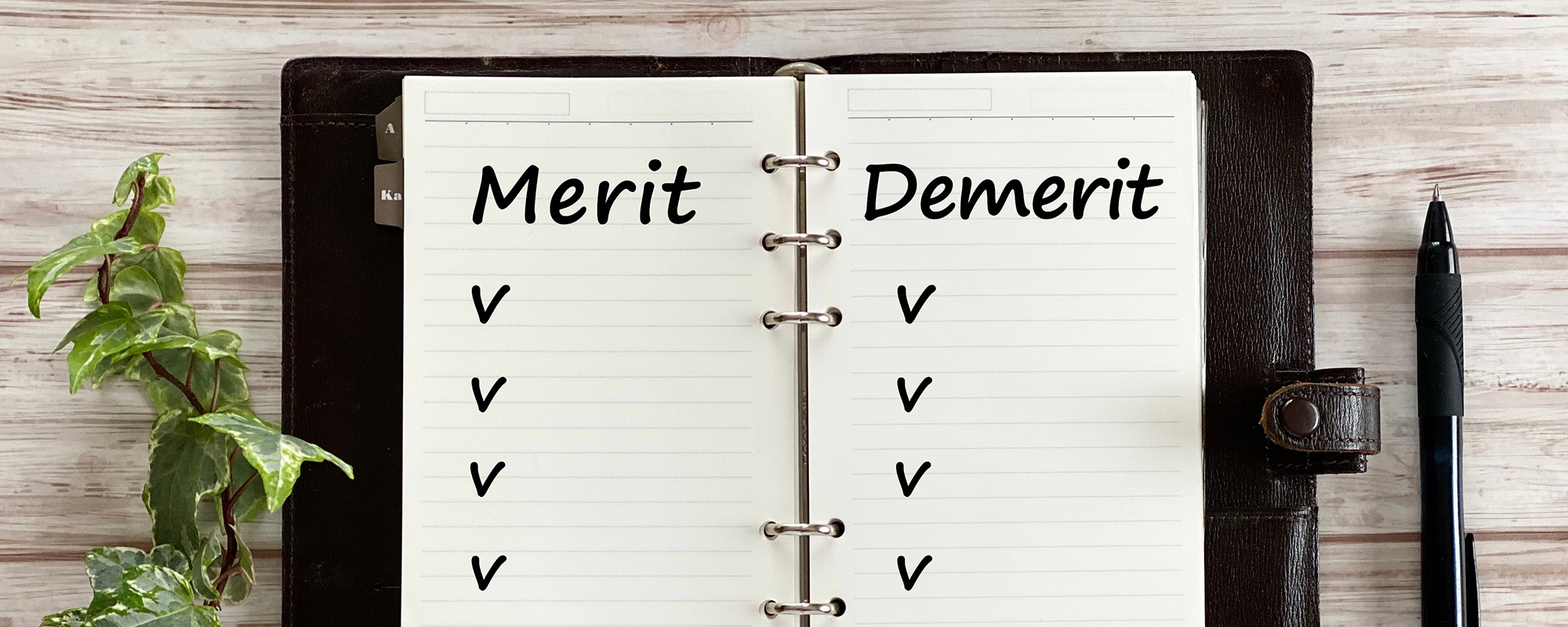
転勤で持ち家を賃貸に出すメリットとデメリット
転勤で持ち家を賃貸に出す場合のメリットとデメリットを詳しく解説します。
メリット
持ち家を賃貸に出す最大のメリットは、定期的な家賃収入が得られる点です。家賃収入を住宅ローンの返済や転勤先での家賃に充てれば、住居費の負担を軽減できます。
さらに、人が住むことで空き家にするよりも建物の劣化を防げるメリットもあります。空き家にしておくと掃除や空気の入れ替えが行われないため、家の劣化が進んでしまいます。その点、賃貸に出して水回りや設備を定期的に使用してもらえば、家の劣化が抑えられるのです。
また、一定期間で賃貸借契約が終了する「定期借家契約」を利用すれば、契約期間終了後に確実に自宅に戻れるため、転勤後の生活プランが立てやすくなります。このように、資産価値を維持しながら収入を得られる点が、賃貸に出すメリットです。
デメリット
持ち家を賃貸に出す際のデメリットとして、入居者とのトラブルリスクが挙げられます。持ち家を賃貸に出すと、家賃滞納や設備の不具合、近隣トラブルなど予期せぬ問題が発生することが考えられるのです。
また、入居者が決まらないことによる空室リスクもデメリットの1つです。入居者が見つからない期間も住宅ローンや固定資産税などの支払いは続くため、赤字になるおそれがあります。特に立地条件が良くない物件や間取りが特殊な物件は、借り手が見つかりにくい傾向にあります。
さらに、「定期借家契約」を締結しても、転勤期間が予定より短くなった場合は契約期間中に退去を求められないため、自宅に戻れないこともあるでしょう。たとえば、3年間の定期借家契約を締結したにもかかわらず2年で転勤から戻ってきても、定期借家契約が終了するまでは持ち家に住むことができません。
持ち家を賃貸に出す場合は、これらのデメリットを考慮して検討する必要があります。
転勤で持ち家を売却するメリットとデメリット
転勤により持ち家を売却する際は、維持費の軽減やまとまった資金が手に入るなどのメリットがある一方で、いくつかの注意点があります。ここでは、持ち家を売却するメリットとデメリットを詳しく解説します。
メリット
持ち家を売却する最大のメリットは、維持費の負担から解放されることです。持ち家を売却すれば固定資産税や住宅ローン、マンションの場合は管理費や修繕積立金などの支払いがなくなり、家計の負担が大幅に軽減されるでしょう。たとえば分譲マンションの場合、売却により月々15万円の住宅ローンと3万円の管理費・固定資産税が不要になれば、転勤先での生活に余裕が生まれます。
さらに、売却によってまとまった資金が得られた場合は、その資金を転勤先で家を購入する際の頭金にしたり、家賃の高い物件を選んだりすることができます。売却後は管理の手間がかからないため、入居者とのトラブルや空室リスクを心配する必要もありません。
デメリット
持ち家を売却する際は、仲介手数料や登記費用、引っ越し費用などの諸経費がかかります。それにより売却後に手元に残る金額が減り、住み替え計画に影響が出るおそれがあります。
さらに、短い期間で元の地域に戻る場合、前の家と同じような条件の物件を見つけるのが難しいケースもあるでしょう。特に人気エリアでは、数年後に戻った際に同じレベルの物件を同じ価格で購入できる保証はありません。
また転勤前に売却する場合、転勤の準備で忙しい中で売却活動を進めなければならず、転勤までに売れないと二重で住居費がかかるリスクもあります。持ち家の売却を検討する場合は、不動産会社に相談しながら万全に準備することが大切です。
転勤で持ち家を空き家にしておくメリットとデメリット
短期間の転勤や愛着のある家を手放したくない場合は、転勤が決まっても賃貸や売却せずに空き家のままにしておく選択肢もあります。ここでは、空き家にしておく場合のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
持ち家を空き家にしておくメリットの1つは、いつでも自分の好きなタイミングで戻れる点です。賃貸に出す場合と違い、契約期間に縛られず転勤期間が予定より短くなってもすぐに自宅に戻ることができます。たとえば、3年の転勤期間が1年で終わった場合でも、すぐに元の生活に戻れるのは大きな安心感につながるでしょう。
さらに、新生活で不要な家具や家電をそのまま置いておけるため、引っ越しの手間や費用を大幅に削減できます。また、家を他人に貸し出さないため、室内が汚れたり設備が故障したりする心配もありません。
デメリット
持ち家を空き家にしておくデメリットは、経済的な負担が大きいことです。住宅ローンの返済に加え、固定資産税や都市計画税、マンションであれば管理費や修繕積立金などの支払いが続くため、転勤先と持ち家の住居費が二重の負担になります。たとえば、月々の住宅ローン10万円と管理費・修繕積立金の3万円、さらに転勤先での家賃が8万円だとすると、毎月20万円以上を支払わなければなりません。
さらに、人が住まない家は劣化が早まるリスクがあります。水回りの腐食や結露によるカビ、害虫や害獣の侵入など、空き家のまま放置すると建物の価値が下がる原因になります。また、空き家は防犯面の心配もあり、不審者の侵入や放火などのリスクも高まります。
このように、空き家の期間が長くなるほどデメリットが増えるため、短期でないかぎり空き家にしておくのはおすすめしません。
転勤で持ち家を賃貸に出す手順と注意点

ここでは、持ち家を賃貸に出す基本的な流れと注意するべきポイントを紹介します。
持ち家を賃貸に出す流れ
持ち家を賃貸に出す流れは次の6ステップです。
- 1. 不動産会社に査定を依頼する
- 2. 仲介・管理を依頼する不動産会社を決める
- 3. 入居者募集・審査を行う
- 4. 賃貸借契約を締結する
- 5. 家を引き渡す
- 6. 管理・運営を開始する
まずは、不動産会社に査定を依頼します。担当者の対応や査定結果を比較するために、複数の不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。中には、市場価格からかけ離れた高値の査定額を提示して顧客を誘導しようとする不動産会社も存在するため、査定価格に根拠があるかどうかを見極めなければいけません。
査定結果が出れば、比較検討して仲介・管理を依頼する不動産会社を決めます。その後、家の貸し出し条件が決定すれば入居者募集が始まり、入居審査を経て契約締結となります。転勤先の新居へ引越し後、鍵を入居者に渡して引き渡しの完了です。転勤先が持ち家から遠い場合は、家賃の集金や修繕の対応などの管理を不動産会社に任せると安心です。
持ち家を賃貸に出す際の注意点
転勤後に持ち家に戻る予定がある場合は、入居者と「定期借家契約」を結びましょう。定期借家契約であれば、契約期間が終わると入居者に退去してもらえるため、戻ってきたときに自分の家に住めます。ただし、契約期間が決められている定期借家契約は借りる側にとって不利な条件であるため、家賃や敷金・礼金を低めに設定するなどの工夫が必要です。
また、住宅ローンが残っている場合は必ず金融機関に相談してください。住宅ローンは基本的にローンを組んでいる人が自分で住むためのものであるため、家を勝手に賃貸に出すと契約違反になるおそれがあります。転勤が理由であれば一時的な賃貸を認めてくれるケースはありますが、トラブルを避けるためにも、あらかじめ金融機関に相談することを忘れないようにしましょう。
条件を満たせば転勤でも住宅ローン控除が適用される
住宅ローンを組んでいる場合、条件を満たせば転勤が決まっても住宅ローン控除が引き続き適用されるケースがあります。ここでは、「単身赴任の場合」と「控除期間内にもう一度持ち家に戻って住んだ場合」の2パターンを紹介します。
単身赴任の場合
単身赴任で家族が家に住み続ける場合は、「所有者が居住しているもの」とみなされ、住宅ローン控除を継続して受けられます。住宅ローン控除は「やむを得ない事情がある場合に限り、一定の要件を満たせば例外的に適用を受けることができる」とされているためです。
単身赴任の場合はやむを得ない事情が「転勤」、一定の要件が「家族が住み続ける」ことに該当します。
参考:国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等」
控除期間内に再び持ち家に住む場合
転勤で家族全員が引っ越した場合、転勤中は控除が受けられませんが、戻ってくれば残りの期間だけ再び控除を受けられます。ただし、住宅ローン控除は「空き家にしていた場合は戻った年から」「賃貸に出していた場合は戻った翌年から」の適用になる点に気をつけましょう。
たとえば、住宅ローン控除が13年で住宅ローン控除を5年受けた後に転勤が決まり、家族で3年間転居して戻ってきたとしましょう。このケースでは、住宅ローン控除を受けられるのは、最初の5年と再入居した後の5年の計10年間です。ただし、持ち家を賃貸に出していた場合は、戻った年の翌年から住宅ローン控除が適用されるため、トータルで9年間の適用となります。
参考:国税庁「住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)」
転勤で持ち家を売却する手順と注意点

転勤が決まり、持ち家を売却する場合の流れや注意点を紹介します。
持ち家を売却する流れ
持ち家の売却は次の手順で進みます。
- 1. 不動産会社に査定を依頼する
- 2. 不動産会社と媒介契約を締結する
- 3. 不動産会社が売却活動を行う
- 4. 買主と売買契約を締結する
- 5. 決済・引渡しを行う
持ち家を売却する際は、まず不動産会社に査定を依頼します。賃貸と同様に、複数の不動産会社に査定を依頼して、対応や査定結果を比較しましょう。依頼する不動産会社が決まれば媒介契約を締結し、売却活動が始まります。購入希望者から内見の申し込みがあれば対応し、条件が合えば売買契約を締結します。その後、物件価格の受領と引き渡しを行えば売却の完了です。
持ち家の売却により利益が出た場合は確定申告が必要です。しかし、「居住用財産の3,000万円特別控除」などの特例が利用できる可能性もあるため、売却により利益が出た場合は不動産会社の担当者や税理士に相談してみましょう。
持ち家を売却する際の注意点
持ち家を売却する際の注意点は、住宅ローンの残債と売却価格を確認することです。特に購入から数年以内の物件は、住宅ローン残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の状態になりやすく、その場合は差額を自己資金で補填しなければいけません。残債額は、住宅ローンを組んでいる金融機関に連絡すれば確認できます。
また、売却のタイミングにも気をつけましょう。転勤前に売却を始めると、生活しながら内見に対応する必要があり、スケジュール管理が難しくなります。「引越し前に内覧してほしくない」「部屋が空っぽの状態で内見してほしい」という方は、引っ越し後に売り出しましょう。ただし、その場合は持ち家が売れるまで、二重で住居費がかかります。
さらに、売却には仲介手数料や印紙税、抵当権抹消費用などの諸経費がかかります。諸経費は、売却代金の5%〜7%程度を見込んでおくと安心です。持ち家を売却する際は、資金計画やスケジュール管理など、不動産会社のサポートを受けながら進めるのがおすすめです。
まとめ
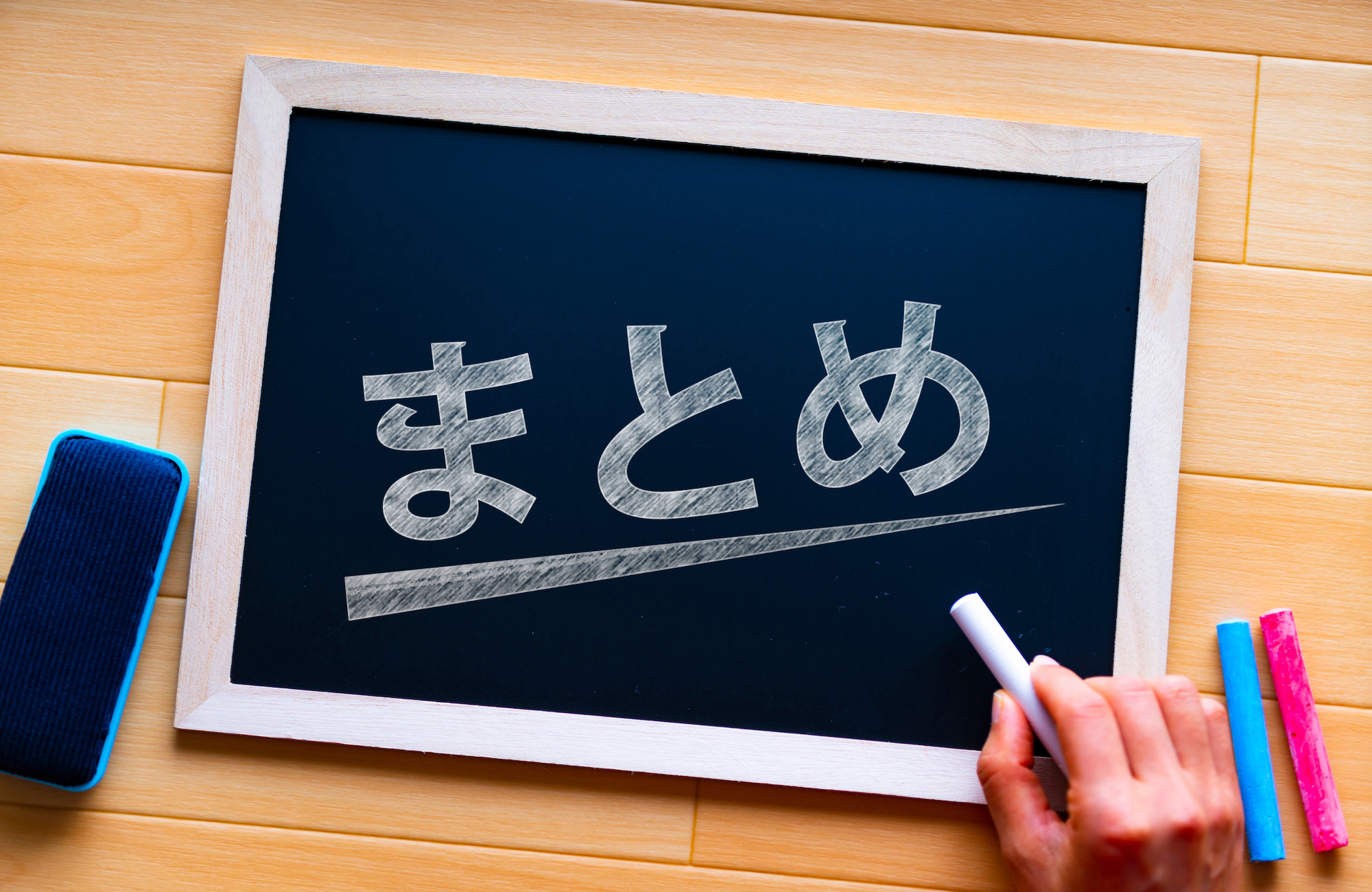
転勤で持ち家を活用する方法として、以下の3パターンが挙げられます。
- 賃貸に出す
- 売却する
- 空き家にしておく
持ち家を賃貸に出すと、定期的な家賃収入が得られる一方で、入居者とトラブルが発生するリスクがあります。売却する場合は、維持費や住宅ローンから解放されるメリットがある反面、スケジュール管理が難しい点がデメリットです。空き家のままにしておくと、いつでも家に帰ってこれますが、長期間にわたり空き家にしていると家の劣化が進んでしまいます。
転勤による持ち家の活用方法は、そのときの状況や家の立地などケースによって異なります。そのため、信頼できる不動産会社を選び、適切なアドバイスを受けることが成功への近道だと言えるでしょう。
センチュリー21住新センターでは、転勤で持ち家の活用方法に悩んでいる方へのサポートを行っています。これまでの豊富な実績とノウハウで、お客様一人ひとりに合わせた活用方法をご提案いたします。
センチュリー21住新センターでは賃貸・売却の無料査定や、空き家管理のご相談を受け付けておりますので、急な転勤で持ち家をどのように活用すれば良いのかわからない方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
